島津氏が薩摩を治め続けられた要因とは?(2014/12/15)

仙巌園〔島津氏別邸跡・庭園〕
鎌倉時代から明治まで同一国を治め続けた稀有な存在である薩摩島津氏。様々な要因が考えられるが、その一番の理由として挙げられるのは?
[投票実施期間]2014年12月15日~2014年12月27日
1.周囲に強国が少なく、領地を脅かされることがなかったため。 |
|
|
2.南端という地勢上、中央政府の介入を受けにくかったため。 |
|
|
3.琉球や諸外国との交易もあり、物資が豊富であったため。 |
|
|
4.本家・分家から有能な当主を輩出し続けることができたため。 |
|
|
5.薩摩隼人と称されるように勇猛な気質の土地柄であったため。 |
|
|
6.その他 |
|
|
「ニッポン城めぐり」利用者のコメント
日向夏隠岐守(2を選択)
端っこで攻めるの大変だし(笑)
海老之介【⊕】太閤(4を選択)
島津にバカ殿なし❗末裔であることを誇りに思う。
瀧乃道摂津守ユズル(2を選択)
遠いし
がんちゃん弾正大弼(5を選択)
最大の危機は関ヶ原合戦後で、あえて家康が領土安堵にしたのは、薩摩隼人の気質に立ち向かった場合、多大な死者を出すのを防ぐのをためらったかと…
式部大輔喜多(3を選択)
南端という立地もあるけど流通経済の基盤があったから治世を維持出来たと思ってます。
願舟近江守(2を選択)
良くも悪くも地勢の影響は大きいでしょう。
昌弾正忠(3を選択)
貿易って、薩摩の特権の一つで、大きな強みだよね。
財力があれば装備は用意できるし、国内国外の情報は勿論のこと、国外経由の国内情報も入手できるし。
治部卿いなばんちゅ(4を選択)
当主が有能だったかもしれないが琉球を攻め、国王を江戸に連れていき、琉球を我が物顔で闊歩していた薩摩に沖縄県民はアメリカ人と同じくらい恨みを持っている人もいる
ミームン中務卿(4を選択)
1,2,3は薩摩地域の地理的要因、5は薩摩人の歴史的背景と地域性、それらを加味して島津家が生き抜いて来たのは、最良の領主を排出し続けてこれる本家、分家のシステムと家臣団構成にあったのでは?
たわけ者征夷大将軍速水右近(6を選択)
薩摩の土地自体が天然の要塞であり、余りにも遠方なので攻め滅ぼすのに何年もかかり莫大な経費がかかるので、所領安堵の和解が現実的な戦略であった。
広開土王談徳(2を選択)
2が一番重要、鹿児島はとおかぁ!そして、家臣団の結束、琉球が近い。
崇徳治部少輔顕仁(6を選択)
島津だから
キョロ左近衛中将ちゃん(2を選択)
地の利は大きなアドバンテージ。優秀な人材居ても討伐される大名多かったけど、薩摩は遠過ぎた。
マヒナ弾正忠(2を選択)
地理的条件はすごく重要だと思います。この時代で海を挟んだ九州の更に南端。そしてそれがどんなに有利か熟知していたのが島津家なんじゃないかな。
⚡ 太政大臣雷権現⚡(4を選択)
南端という地理的要因は大きいが、その前に家が存続してきた事が見事。暗君無し!
勘解由次官くわんひょうえ(5を選択)
島津義弘を筆頭に勇猛な人材によるところが多いと思います。
兵力の違いにも狼狽えず勝利をおさめるということは作戦だけではなく兵の一人一人が戦闘力が高かったようにも思います。
快刀乱麻きらり(2を選択)
まさに地勢
(3を選択)
明、琉球との交易で得た富は、戦費や献上品になりその都度島津が生き残る要因になったと思います。
豊後守大吾郎左衛門(4を選択)
とにかく偉人が多いね!
赤備えみみなが内蔵頭(3を選択)
中央 から 遠く 蜜貿易が あったればこそ 賄賂ざんまい で いられた で ござる !
古楽侍従広家(6を選択)
選択肢すべて。
あきえもん近江守(2を選択)
どれも影響あった。敢えて選ぶなら2かな。情報あまりない、攻めるのも大変。役人や兵の駐屯も難しい。大名を残せば民は静かで、大名は服従させられると思ったのでは。例え挙兵しても中央まで遠いし。
右近衛少将 乱朱(5を選択)
薩摩という南端から上り詰めた島津が好きだから、これ以外の理由は考えられない!
野呂利左衛門督休三(2を選択)
理由は消去法。日向、肥後はともかく大友がいた(幸にも大内と抗争)。交易は筑前、肥前もしていた。貴久まで一族抗争。戦は基本的には数が問題。よって2に一票。
にゃにゃーにょ豊後守(2を選択)
わざわざ強兵のいる痩せた土地(シラス台地のため)に攻め込もうとは思わないでしょう。後の統治も大変そうだし。
青き巨星弾正少弼かみ(4を選択)
人財豊富(ザイは財産)な事が一番。
柴崎権大納言幸助(2を選択)
独特の文化を認めながら手なずける方が中央政府には得策であったと思います♪
プー(3を選択)
貿易効果は、すごいと思います。
時の権力者に相当な貢ぎものをしたおかげ。
柿崎信濃守景家(6を選択)
地形的や、土地柄、勇猛果敢だったり、他国の勢力の介入がなかったりと考えられますが、やっぱり最後は人徳ですかな?
やえがし(5を選択)
気質はかなりあると思う。
ドン・ティファニー豊後守(2を選択)
やはり 中央から 離れているとよくも悪くも…影響が…ないのかと(^-^;)
勘解由長官泰右衛門(2を選択)
やっぱり中央からは遠いです
黒田左近衛大将走兵衛(2を選択)
そりゃ南の備えなしに北の隣国攻められますからねぇ(^o^)v
tomcat 織部佑(3を選択)
会津としては面白く無いですが
すごいのは認めざるを得ないです
勝之助若狭守(2を選択)
やはり都から遠いのである程度自由に(秘密利に)出来たのではないでしょうか。
まさ宮内卿猛虎(4を選択)
分家等から系列武将が輩出出来たのは、郷中教育思想・負けない精神の薩摩魂が、昔から伝わっていた。15代貴久は内紛の鎮静化・薩摩・大隈・日向の統一の基礎を固めた。
刑部卿狩家中将悠朱庵雄基(2を選択)
やはり日の本の南西端で脈々と続く鎌倉以来の名家の裔という眼に見えぬ強大なカリスマ性と、日新斎の政治力が子孫に受け継がれて“島津に暗君無し”の歴代当主の下、人材育成・登用に力を注いだ結果に他ならぬ。
東(2を選択)
琉球を除くと、日本列島の南端だった為に攻められる方向が限られた。加えて、度胸溢れる薩摩隼人の気質。伝統から来る高い知性。
小枝左近衛少将(6を選択)
1以外すべてだと思います。歴史上原因が一つだけということはほぼないです。
ミーです越後守(2を選択)
やっぱり、場所的に他の勢力が入りにくいように思います。あそこを取ってもなあ~って。角を取って勝ちは、オセロくらいでは?
しぐ安房守(6を選択)
鎌倉の士風(司馬遼太郎「街道をゆく 三浦半島記」)
銀英6阿天暮郎(4を選択)
文字通り「島津に暗君なし」。これはなかなか稀有なことです。
芦屋能登守虎吉(6を選択)
家康に呼び出されても、江戸まで行く旅費がなかったから!
江里子(3を選択)
やっぱり貿易している所は強いだろう。物資に余裕できそうだし、時代を先取り
田部朝臣土持安房守(6を選択)
日本国内で見れば領する旨味が無い土地であると見えるから。この地の利点は他国者には秘密。
故に島津一族内で取り合っていただけで、一見ずっと島津一族が治めている。
余所なら姓が出水とかになってますね。
いえろーまん讃岐守(2を選択)
鹿児島遠いし。
綱島出雲守八雲(6を選択)
中国や朝鮮からの侵略がなかったから。
黒野 淡路守 貞泰(2を選択)
歴史シュミレーションゲームでも 端っこの国は守りやすいですよね!
さくらゆき隊左近衛大将びりー(3を選択)
2番も大いにありうるが、やはり琉球や支那との交易は莫大な蓄財になったと思います。
鶴亀仙人(2を選択)
これしかないでしょ?
127 件中 1〜50 件目を表示中

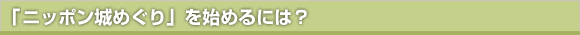
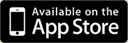 ■iPhone
■iPhone








